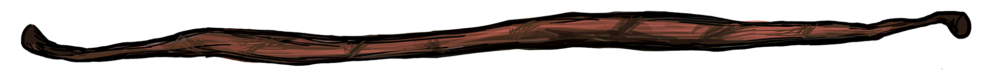バニラ抽出とペースト(パテ)の歴史
バニラ・エッセンス(バニラビーンズ抽出液)の歴史とバニラペーストの発明は、人類の有史以前からコンピュータが普及した産業革命後の時代まで続きました。プランフィリアの原産地であるメキシコでは、ぶら下がって腐りかけている(しかし、とても芳香を放つ)つるを這わせ、その香りに魅了されたメキシコ人は、先端のとがった石や斧でさやを荒くすりつぶしたり、さやをはぎ取って中身をこそぎ落とし、水のようなハイドロゾル(芳香水)やどろどろのペースト状のものを作りました。
アステカ人は、アリが受粉させるテオブロミンを含むカカオの木(砂糖不使用)を、ミツバチが受粉させるバニラの基調を持つ、100%ダークチョコレートのような味わいのチョコレートドリンクとして使用していました。今日、私たちは実際に、米国と日本のいくつかのバー向けにこれを生産しています(「アステカ・オリジナルドリンク」製品を参照)。
16世紀のスペインの巨大帝国は、17世紀のイングランドの私掠船による略奪(おそらくイスパニョーラ島やポートロイヤル付近でもプランティフォリアを略奪した可能性がある)に先立ち、アステカの中央集権的社会でバニラを発見しました。そして、新世界との大西洋貿易により、バニラがヨーロッパに紹介され、ヨーロッパ人はインド洋と太平洋の世界中にバニラを植えようと、不毛で挫折感を抱きながら試みました。
そして、ついにエドモンド・アルビウス(Edmond Albius)のブルボン法の発明によって、メキシコミツバチを人間の手に置き換えることが可能になりました。こうして、世界で最も労働集約的な作物がマダガスカルに根付き、教え込まれ、プランフォラは現代の主要な生産品へと増殖しました。そして、バニラ海岸として知られるSava(サヴァ)は、今でもその大部分を占めています。
1800年代、エタノールアルコール(つまりサトウキビラム、あるいは粗製現実的な表現で言えば、バニラが栽培され出荷された場所を考慮した)の製法が、フランス語圏の植民地における「ラム酒アレンジ」に使用されていました。フランス人や外国人の移住者は、熟成したバニラビーンズを刻んでアルコールに漬け込み、そのまま置いておくと、従来の抽出液が作られるという方法でした。この簡単な手順が、バニラ風味を菓子やデザート、製菓に取り入れるための最も一般的な抽出方法となりました。
イギリスとフランスが最大の使用国であり、イギリス帝国が世界的な影響力を失った後、アメリカでの使用は着実に増加しました。最終的に20世紀後半には、バニラエッセンスの生産の中心はアメリカに移り、第二次世界大戦後には、冷蔵機能を備えたテレビや州間高速道路、スーパーマーケットが、60年代から90年代にかけて消費文化が急成長する中、食品および飲料におけるバニラの普及に最適なアメリカのモデルとなりました。
近代的な研究所が建設された後、食品科学はより臨床的または化学的になり、加工や大規模農業に莫大な投資が行われるようになりました。フレーバー科学および関連する食品科学研究所では、溶剤、圧力、熱、および 複雑に連結した容器や調理器、圧力弁などを用いて、バニラの風味特性を変換するさまざまな方法を開発しました。これにより、1900年代半ばの近代的な抽出作業は、酒屋のラム酒貯蔵庫というよりも蒸気船の機関室に似たものとなりました。2000年代には、科学技術者が人工的でありながら本物の味に忠実な、マダガスカル産バニラのメリットを賞賛し、その実現を保証するようになりました。
バニラは、230以上の分子化合物から成り、それらが相互作用することで、科学が作り出すことのできるフランケンフードよりもさらに複雑な風味を作り出しているのです。 20世紀後半には、皮肉にもよりシンプルで手間がかかりますが、明らかに困難な、風味に優れた抽出方法が一般的になり始めました。Cooks(Lochhead)のような抽出業者は、機械化された利益率の高い大量生産よりも品質に重点を置いています。溶剤を使用するものの、ゆっくりと低温で風味を損なわずに保つ冷温抽出法は、いわば、抽出液に高忠実度のバニラの香りを付着させるために使用されてきました。 また、非常に高い圧力は、ある意味で、マダガスカル産の鞘の風味をより多く引き出すものでもあり、化粧品業界では、低温でも超臨界CO2を使用して有効成分を科学的に抽出する方法が考案されました。
技術がコンピュータ・モデリングの時代に進歩したことで、バニラの分子や複雑な化合物を観察できるようになりました。ラボで再現することはできなくても、抽出業者や香料メーカーは、豆の魂ともいえるものを抽出液により多く取り入れる技術を開発し、少なくとも何が最も効果的かを記録できるようになりました。40年後、インドネシアとウガンダは、自分たちには理解できない市場に突然放り込まれ、土壌から乾燥、そして畑での手作業によるマッサージ、そして風味を反対側から引き出すという冷たくゆっくりとした大変なプロセスに至るまで、味の微妙な違いを育んできた芸術的な事業に工業的な考え方を適用しました。模倣国における魂のない機械化は、バニラの風味の魂が最終的な味に変換されないため、オークの木や水っぽいチョコレートの殺菌ジュース(ウガンダの場合)のような、あるいはスモーキーでオークの香りが強く針葉樹のような鋭い酸味(インドネシアの場合)のような、最悪のバニラ液を生み出す結果となりました。
フランス領の海外で育まれたタヒチ産バニラと島の手仕事産業は、マダガスカル産バニラの卓越性と肩を並べる別の風味となり、「タヒチ産のオレンジとマダガスカル産のリンゴ」のように、どちらも経験を経て卓越性を獲得しました。